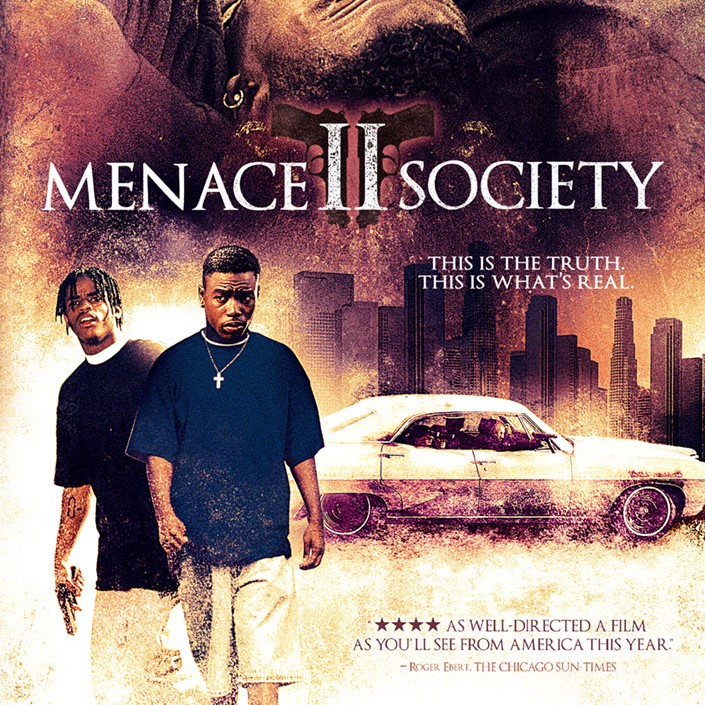誰もが「死体探し」の青春モノとして記憶に留めるロブ・ライナー監督の『スタンド・バイ・ミー』を分かりやすく、どこかシニカルに引用しながら、「Boyz」たちの青春が幕を開ける。人が死ぬことがまったく珍しくない地域で、少年たちは遭遇した死体をどう見たのだろうか。映画としての演出意図は、言うまでもない、未来の暗示である。彼らが目にしたのは、「未来の自分」だったか、それとも「絶対に避けたい未来」だっただろうか。
安易で、感傷的な連想だとは思いつつ、映画を観終わった時、真っ先に聴きたくなったのは本作に出演しているアイス・キューブが所属したN.W.Aの「Boyz-N-The Hood」ではなく、2パックだった。特に、暴力の連鎖によりストリートで次々に息絶えていく若きギャングスタ―たちを思う「Life Goes On」を何度か聴き直し、そこで歌われているものがなんとなく分かったような気がした。
もっとも、本作でメインに描かれる青年たちは別にギャングスタ―ではない。荒廃したロサンゼルスの住宅街で、リッキーはアメフト選手を夢見ていて、その幼馴染のトレは大学進学によって現状からの脱出を目指す「普通の」青年たちである。が、ストリートのしがらみの中で人生のコントロールを少しずつ失っていく過程はギャングスタ―のそれとほとんど変わらないのではないか、とも思う。
事実、この親友同士の二人組は、拳銃をチラつかせて虚勢をはったりしているリッキーの兄・ダウボーイを媒介に、ギャングたちの世界とうっかり交わることになる。暴力が容赦なく行使される世界。そこで先に逝ってしまった者と、残された者。そこで閉ざされた人生と、それでも続いていく人生。ある時代のアメリカを、黒人として生きるとはこういうことだったのだと、思わず言ってしまいたくなる。
もちろん、そんな権利は私にはないし、アメリカ黒人というだけで生活条件を一般化することはすでにできない時代だったはずだ。が、入門書を何冊か読んだ今、本作には都市部に取り残された80年代後半当時のアメリカ黒人が置かれたある種の典型的状況――貧困、家庭崩壊、犯罪や疾病、麻薬汚染、警察官の暴力など*1――が(おそらくは現実を上塗りする形で)描かれていることが分かる。「階層の分極化」や「低賃金」、「十代での妊娠」、「母子家庭」も加える必要があるだろう。
このうち、疾病(エイズ)や麻薬(クラック)は『ドゥ・ザ・ライト・シング』でスパイク・リーが(おそらくは意図的に)描かなかったものでもある。一方のシングルトンは、自伝的作品である本作において、ある意味では「お決まり」でもあるこれらの要素をすべて盛り込んでいる。政治的効果まで見込んだ上での問題提起を企てるよりも前に、ありのままの現実を描写することを選んだのだろう。その意味で、本作は非常にラップ的と言えるのではないか。
実際、『ドゥ・ザ・ライト・シング』が人種間の対立をメインに描いたのに対し、本作はアメリカ黒人同士の内部対立に意識が向けられている。その意図は、レイシャル・プロファイリングを行う警官までもが黒人である点にもっとも象徴的に凝縮しているように思う。もはや、「ファイト」すべき相手は自明ではないのだ。帰宅後、普段は温厚なトレがあまりの屈辱に行き場のない怒りを爆発させる場面は本作のハイライトとなる。
さらに付け加えるなら、学生時代に(おそらくは未婚のまま)トレを産み育てたであろうトレの両親が会食するシーンを思い出してもいい。白人だらけのレストランに2人が上等な身なりで溶け込む場面、何か良くないことが起こりそうで身構えてしまうのだが、何かが起こりそうで何も起こらない。間違っても他の客にエスプレッソを頭からかけられたりはしない。もう公民権運動やロング・ホット・サマーの季節ではないのだ。
この時代、アメリカ黒人の地位は「全体としては」向上し、改善した。トレの両親はそれを体現した存在である。だからこそ、トレたちの暮らす「地元」は世界から忘れられた場所になってしまったのだろう。「それは君たちの努力不足だろう」という論法で。アメフトも勉学もなく、ただ刑務所と地元を行き来するダウボーイのやるせなさ。「父親」が不在の世界で、「遅かれ早かれみんな死ぬ」という感覚が街全体を飲み込んでしまっている。
だからこそ、こうした「地元」から脱出するためのチケットとして「父親からの教え」が描かれている点については、正論がゆえの違和感があり、「母子家庭」社会に対するアンサーには今も当時もならないのではないかと思ってしまった。かと言って、修士号を持つトレの母親が体現するような「勝ち上がり」を全員に求めるのも現実的ではないだろうし、本作が全体として表現するのはやはり、世界から忘れられた街で、それでも生きるということのリアリズムだろう。
『ドゥ・ザ・ライト・シング』評と同じ結論になってしまうが、こうした告発の表現が、2022年の今もなお現在性を失わない点に、本作の批評的な意義と、空しさが凝縮している。もちろん、それはこの映画の過失ではないけれど。また、告発という点に限れば、スマートフォンによる撮影とSNSによる拡散という手法がすでに本作を追い抜いているという言い方もできるだろう。BLM運動を持ち出すまでもなく、それは今を生きるトレたちの力となっている。
だからこそ逆に、ブラック・ムービーは今、何を描くべきなのか、ということを考えさせられた。読むべき本も、考えるべきことも山積みではあるが、「ロング・ホット・サマー特集」の延長として、もう何作か観てみたいと思う。
******
監督:ジョン・シングルトン
原題:Boyz n the Hood
劇場公開日:1991年7月2日
youtu.be